Written by WizLANSCOPE編集部

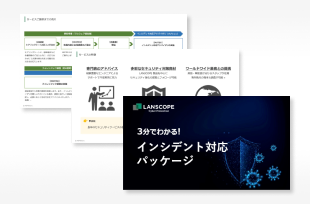
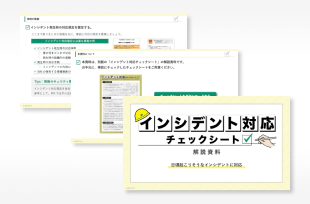
目 次
IT分野におけるインシデントとは、システムやサービスの運用に重大な影響を及ぼす障害や問題を意味します。
その中でも、マルウェア感染や不正アクセス、内部不正など、情報セキュリティ上の事故や問題は「セキュリティインシデント」と呼ばれます。
こうしたインシデントを適切に管理することで、発生リスクを低減したり、発生時の影響を最小化したりすることが可能です。
本記事では、インシデントの概要やインシデント管理の重要性、流れなどを解説します。
▼本記事でわかること
- インシデントの概要
- インシデントが発生した場合の影響
- インシデント管理の重要性
- インシデント管理の流れ
「インシデント」および「インシデント管理」の基礎を知り、有事の際の対応の迅速化につなげたい方はぜひご一読ください。
インシデントとは

「インシデント」とは、予期せぬ事象や事件を指す言葉です。
特にIT分野においては、システムやサービスの運用に重大な影響を及ぼす障害や問題を意味します。
具体的には、システムのダウンタイム、データ損失、業務の停止などが該当します。
アクシデント・ヒヤリハットとの違い
インシデントと混同しやすい言葉として「アクシデント」や「ヒヤリハット」が挙げられます。
アクシデントは「事故」を意味し、すでに事故が起こっている、または損害が発生している状態を指します。
一方でインシデントは、事故が起きる一歩手前、もしくは事故は発生したものの、重大な被害には至っていない状態を指します。
ヒヤリハットは、製造や医療の分野で主に使われる用語で、重大な事故には至らなかったものの、場合によっては事故につながりかねない出来事を指します。
「重大な被害はない」という点ではインシデントと共通していますが、ヒヤリハットは主に人的ミスが原因で発生するのに対し、インシデントは、自然災害やサイバー攻撃など、人的要因以外も含む点で異なります。
| インシデント | ・事故が起こる一歩手前、または事故は起こったものの重大な被害は発生していない状態 ・人的ミス、自然災害、サイバー攻撃など、多様な要因を含む |
|---|---|
| アクシデント | ・すでに事故や損害が発生している状態 |
| ヒヤリハット | ・人的ミスが原因で、重大事故には至らなかったが、発生すれば事故になり得た状態 |
インシデントの中でも注目されている「セキュリティインシデント」

情報セキュリティの観点から発生する異常や脅威は、「セキュリティインシデント」と呼ばれます。
セキュリティインシデントには、マルウェア感染、不正アクセス、フィッシング、内部不正などが含まれ、これらは組織の機密情報や事業継続に深刻な影響を引き起こす可能性があります。
| マルウェア感染 | ・悪意あるソフトウェアである「マルウェア」に感染させることで、情報の窃取、ファイルの破壊、システムの乗っ取りなどを引き起こす攻撃 |
|---|---|
| 不正アクセス | ・アクセス権限を持たない第三者が、情報システムやサービスに不正に侵入する行為 |
| フィッシング | ・送信者を装った電子メールやSMSを送信や、正規サイトと酷似した偽サイトの利用などによって、ターゲットをだまし、個人情報や認証情報を盗み取る攻撃 |
| 内部不正 | ・組織内部の人間が悪意を持って、または不注意に情報システム・データに対して不正なアクセスや操作を行うこと |
インシデントが発生した場合の企業への影響

万が一インシデントが発生した場合、想定される影響としては以下のようなものが挙げられます。
- 業務の停止
- 損害賠償や復旧費用の発生
- 社会的信用の低下
例えば、マルウェアの一種であるランサムウェアに感染すると、重要なデータが暗号化されてしまい、業務の継続が困難になる恐れがあります。
さらに、感染原因の特定やシステム復旧に要する調査・復旧費用、また必要に応じて新たなセキュリティツールを導入するための費用が発生することも想定されます。
加えて近年のランサムウェア攻撃では、データを暗号化する前に情報を窃取し、「身代金を支払わなければ盗んだデータを公開する」と二重の脅迫をするケースが増えています。
企業がこの要求に応じない場合、窃取された情報がダークウェブなどに公開される危険性があります。
仮に顧客情報などの機密データが流出・公開された場合、社会的な信用が低下するだけでなく、損害賠償を請求されるリスクも発生します。
インシデント管理の重要性
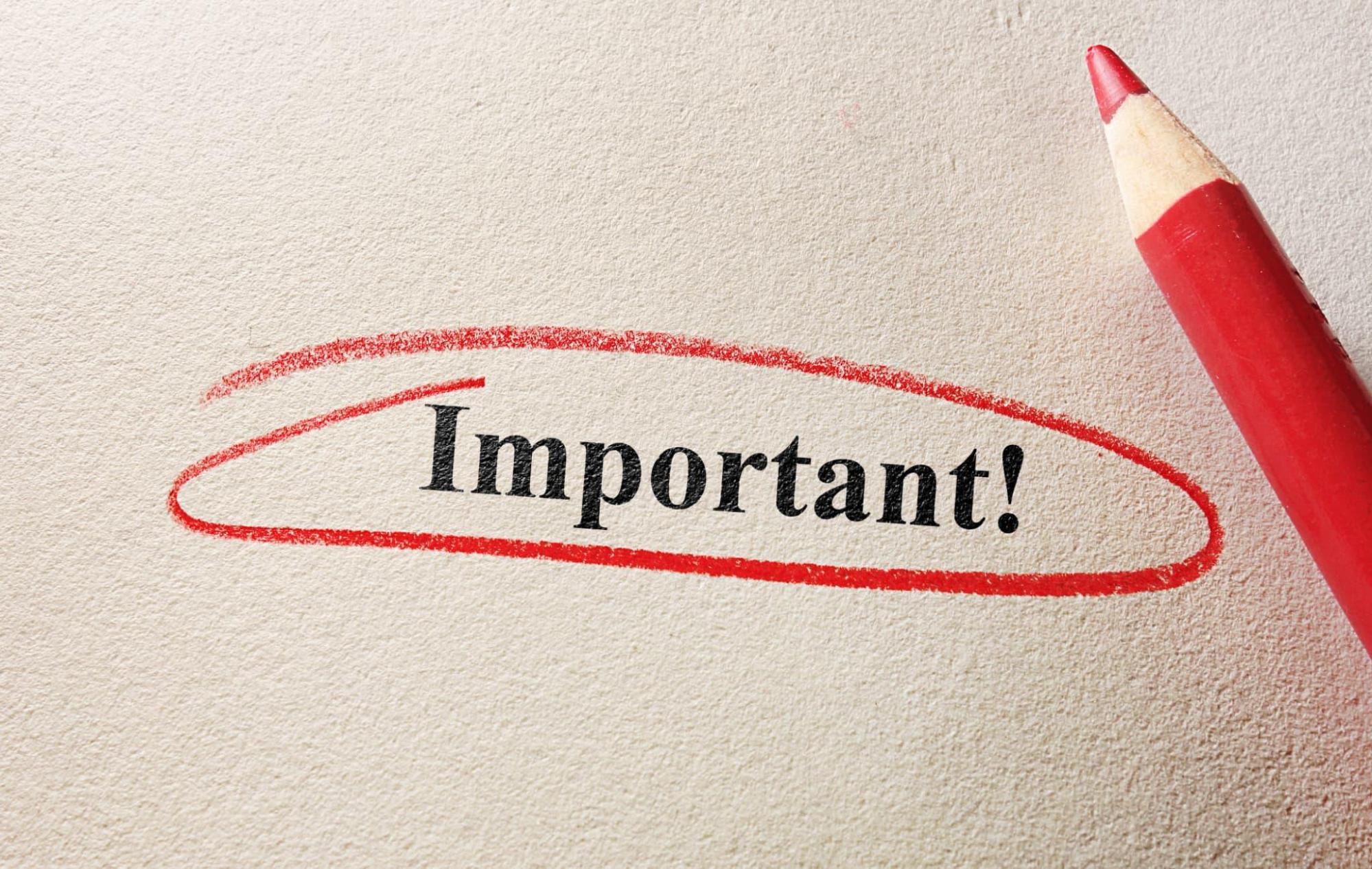
インシデント管理とは、ITサービスの提供中に発生した予期せぬ事象(インシデント)に対し、迅速に記録・対応・解決を行うプロセスを指します。
このプロセスは、インシデントの再発防止および対応スピードの向上の観点から極めて重要な役割を担います。
再発防止のため
インシデントの発生を完全に防ぐことは困難ですが、各インシデントには必ず特定の原因や環境要因が存在します。
これらの要因を調査・分析し、根本原因の特定と恒久的な対策を講じることで、同種のインシデントが繰り返されるリスクを大幅に低減できます。
対応スピード向上のため
すべてのインシデントを完全に防ぐことは難しいため、被害を最小限に抑えるには、発生時の初動対応の速さが重要になります。
迅速かつ正確な初動対応を実施するには、あらかじめインシデント対応フローを整備し、早期の検知・報告・エスカレーションが可能な体制を整えておく必要があります。
さらに、インシデント対応記録やナレッジベースの整備により、過去の事例に基づいた判断が可能になり、次のようなメリットが得られます。
- 類似インシデントへの迅速な対応
- 対応手順の標準化と属人化の防止
- 情報共有によるチーム全体の対応力向上
これらの取り組みにより、結果として被害の拡大を防ぎ、業務への影響を最小限に抑えることができます。
また、BCP(事業継続計画)の強化にも大きく貢献します。
インシデント管理の流れ

ここでは、IPAの「中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」を参考に、セキュリティインシデント管理の流れを解説します。
- ステップ(1):検知・初動対応
- ステップ(2):報告・公表
- ステップ(3):復旧・再発防止
それぞれのステップでどのような対応を行うのか確認していきましょう。
出典:IPA│中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き(2024年7月)
ステップ(1):検知・初動対応
システムで異常な動作が発生した場合や、外部からの通報を受けた場合は、速やかに情報セキュリティ責任者に報告し、対応体制を立ち上げます。
初動対応では、感染・侵害の拡大を防ぐために、ネットワークの遮断、端末の隔離、システムの一時停止などの措置を講じます。
対応の責任者や関係者の役割分担を明確にし、迅速に対応できる体制を整えましょう。
ステップ(2):報告・公表
インシデント発生後は、社内外への適切な情報共有と報告が求められます。
特に、顧客や取引先に影響が及ぶ場合は、速やかに第一報を発信し、状況説明や謝罪を行います。
さらに、個人情報保護委員会、関係官庁、警察等への届け出が必要となるケースもあるため、法令や社内規定に基づいて対応を検討しましょう。
また、問い合わせ窓口の設置や、被害者への説明・補償対応など、信頼回復に向けた適切なコミュニケーションも欠かせません。
ステップ(3):復旧・再発防止
インシデントの原因調査と復旧は、対応プロセスの中核をなす重要なステップです。
まず、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうしたか)の視点で事実関係を整理し、ログやデータの証拠保全を確実に行います。
また、必要に応じてフォレンジック調査を行い、詳細な原因を明らかにしましょう。
そのうえで、システムの修復・データ復元・機器の入れ替えなどの復旧作業を行い、完全に復旧できたことを確認したうえで、業務を再開します。
最後に、再発防止策の実施も行いましょう。
具体的には、ルールや体制の見直し、従業員への教育強化、技術的対策の導入を行い、組織全体の対応力を高めます。
さらに、復旧後の振り返りを実施し、対応プロセスの課題を整理して改善を継続していくことで、インシデント対応力の成熟につながります。
セキュリティインシデント対応の詳細については、以下の記事もご参照ください。
インシデント管理のポイント

最後に、実践的かつ再現性の高いインシデント管理を実施するためのポイントを4つ紹介します。
- インシデント対応ルールの整備
- インシデント対応の記録とナレッジ化
- アラート対応の効率化・自動化
- 対応状況の「見える化」とチーム連携の強化
詳しく確認していきましょう。
インシデント対応ルールの整備
セキュリティインシデント発生時に備え、事前に対応ルールやエスカレーションフロー、対応責任の明確化を定めておくことが推奨されます。
定めておくことが推奨される項目は以下の通りです。
- 対応の優先度(重大度)の基準を決めておく
- 上司や専門チームへのエスカレーション条件を明確化しておく
- 対応時に必要な情報(日時、影響範囲、原因など)を整理しておく
このような項目を事前に明文化し、全関係者に周知徹底しておくことで、万一緊急事態が発生した際でも、担当者が迷わずに適切に対応できるようになります。
また、定期的に見直しを実施したり、実践的な訓練を実施したりすることも重要です。
インシデント対応の記録とナレッジ化
過去のセキュリティインシデントを体系的に記録・分析し、蓄積・検索できる仕組みを作っておくことで、対応精度と再発防止策の品質向上が期待できます。
ナレッジベースに記録すべき情報の例としては、以下が挙げられます。
| 発生したインシデントの概要 | ・発生日時 ・影響範囲 ・発生原因など |
|---|---|
| 実施した対応 | ・具体的な手順 ・対応時間 ・使用したツールなど |
| インシデント対応から得られた教訓 | ・再発防止策 ・運用改善点など |
ナレッジベースを適切に管理・活用できる体制を構築することで、類似のインシデントが発生した際の迅速な対応が可能となり、対応の属人化を防ぐことができます。
アラート対応の効率化・自動化
セキュリティツールのアラートを、すべて手作業で確認するのは非現実的です。
アラート過多を防ぐためには、アラートの優先度判定(トリアージ)と、自動対応の仕組みを整備することが重要です。
また、外部ベンダーによるMDRサービスなどをセキュリティツールと併用することで、運用リソースの最適化が図れます。
対応状況の「見える化」とチーム連携の強化
複数部門・外部関係者が関与するセキュリティインシデントでは、対応状況の可視化と迅速な情報連携が重要です。
実務で求められる「見える化」の要素としては、以下の項目などが挙げられます。
- 対応ステータス(例:検知→分析→封じ込め→復旧→報告)の進捗トラッキング
- 各対応フェーズでの担当者・対応内容・タイムスタンプの記録
- 経営層向けのダッシュボード表示(影響範囲・事業インパクトの見える化など)
インシデント対応の過程では、関係者全員がリアルタイムで状況を把握できる環境が必要です。
インシデント管理ツールを導入し、対応の一元管理とログの自動記録を行うと、より効率的に実施できるでしょう。
セキュリティインシデントの早期解決を支援する「インシデント対応パッケージ」

ランサムウェア感染や標的型攻撃といったセキュリティインシデントに直面した際、限られた人員やノウハウでは、対応しきれないケースも少なくありません。
そういった際に活用したいのが、外部の専門家によるインシデント対応支援サービスです。
「LANSCOPE サイバープロテクション」が提供する「インシデント対応パッケージ」は、フォレンジック調査の専門家が、サイバー攻撃の原因特定から封じ込め、復旧支援までを一貫して支援するサービスです。
フォレンジック調査のスペシャリストが、被害の最小化と早期の事業復旧に向けサポートします。
▼インシデント対応パッケージの特長
| 専門家によるフォレンジック調査 | デバイスやネットワークの調査を通じて、攻撃の痕跡を解析 |
|---|---|
| 影響範囲の特定と封じ込め | 被害の拡大を防ぐための緊急対策を実施 |
| 復旧支援とアドバイス | 今後の対策やセキュリティ強化に関するコンサルティングを提供 |
| 柔軟なオプション対応 | ネットワークログ解析、保全作業、報告会など、ニーズに応じた追加サービス |
「自社で復旧作業が難しい」「攻撃の経路や影響範囲の特定を専門家に任せたい」という方は、ぜひご検討ください。
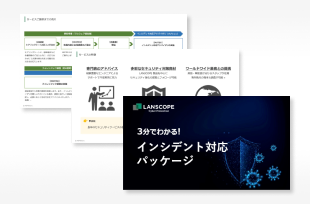
まとめ
本記事では、「インシデント」をテーマとして、インシデント管理の重要性や流れ、インシデント管理のポイントなどを解説しました。
本記事のまとめ
- IT分野における「インシデント」とは、システムやサービスの運用に重大な影響を及ぼす障害や問題を意味する
- 情報セキュリティの観点から発生する異常や脅威は「セキュリティインシデント」と呼ばれる
- インシデントが発生すると、企業には「業務の停止」「損害賠償や復旧費用の発生」「社会的信用の低下」などの被害が引き起こされるリスクがある
- インシデント管理は、「再発防止」および「対応スピードの向上」の観点から極めて重要
- 適切なインシデント管理を行うためには、「インシデント対応ルールの整備」「インシデント対応の記録と再利用(ナレッジ化)」「アラート対応の効率化・自動化」「対応状況の「見える化」とチーム連携の強化」といったポイントを押さえることが重要
適切なインシデント管理を継続的に実施することで、万一インシデントが発生した場合にも、被害の最小化や迅速な復旧が可能です。
企業・組織全体で改善を図り、インシデント発生時に迅速かつ的確な対応ができる体制を整えましょう。
本記事で紹介した「LANSCOPE サイバープロテクション」の「インシデント対応パッケージ」は、サイバー攻撃の原因特定から封じ込め、復旧支援までを一貫して支援するサービスです。
「マルウェアに感染したかもしれない」 「サイトに不正ログインされた痕跡がある」 など、サイバー攻撃を受けた事後に、いち早く復旧するためのサポートを受けたい場合はぜひ活用をご検討ください。
また、「日常で発生するインシデントへの対応」を理解する上で役立つ、チェックシートもご用意しました。
ぜひ自社のインシデント管理体制の見直しにご活用ください。
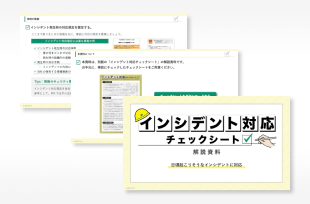
おすすめ記事








