イベント・ニュース
情シス担当者が知っておくべきITトレンド RPA(Robotic Process Automation)
Written by aki(あき)
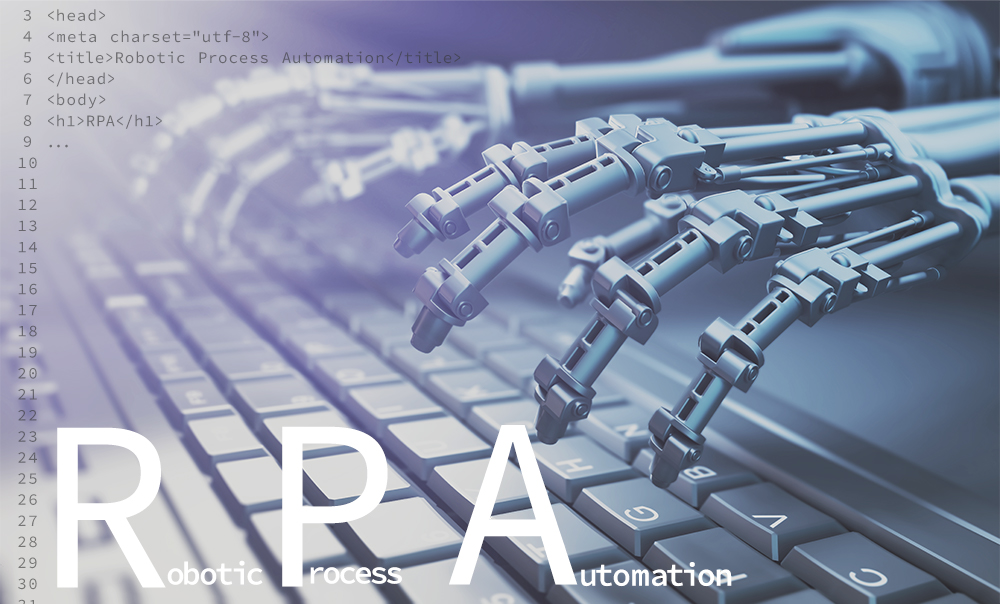
【目次】
・日々の業務を手伝ってくれるRPAとは
・RPAの事例
・代表的なRPAツール
・RPAが注目されている理由
L 技術の進歩
L 働き方改革
L AIの普及
・RPAの普及による情シス業務の変化
L RPAの普及で情シスに新たな業務が生まれるかも
・RPAとAI
・まとめ
日々の業務を手伝ってくれるRPA(Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション)とは
RPAとは、人間が行う作業を自動化する技術です。事前に定義した作業フローに従って、入力や計算、更新、出力といった定型業務を自動化することが可能になります。RPAが活用しやすい業務としては次のようなものがあります。
・一定のルールに従って繰り返し行われる作業
・構造化されたデータを扱う作業
・アプリケーションを使う作業
・標準化された作業
・ヒューマンエラーが発生しやすい作業
RPAを導入することで、今まで人間が行っていた単純作業を自動化することができ、より重要な業務に時間を割くことができるようになります。
RPAの事例
実際にどのような場面でRPAを活用するかを理解できるように、一般的なRPAのユースケースをまとめました。
■一般的なビジネス業務
データの移行や入力業務
OCR等からExcelにデータを入力したり、あるシステムのデータを別のシステムのデータに移行する作業を人が手作業で行うと、少なからず入力ミスが発生してしまいます。
このような業務をRPAに任せることで、入力ミスを防ぐことが可能です。
RPAを活用すれば、スキャンされたドキュメントや画像、OCRなどあらゆるフォーマットからデータを抽出することが可能です。
定期報告書の作成と配布
定期的なレポートの作成もRPAの得意分野です。RPAを活用することで、情シスが担当しているシステムの運用報告書や、営業チームの進捗報告書などを自動生成し、関連するメンバーにメール送信まで自動で行うことができます。
また、システムの運用報告書を自動生成した上で分析し、重大度に基づいてメール送信するメンバーを変更するといった柔軟な対応も可能です。
メールの送信業務
情シスが、社員からのシステム申請メールやアカウント作成依頼メールなど、システムの処理に関する応答メールを手動で作成するのは大変です。特に頻繁に送信する場合は、RPAの活用が効果的かもしれません。
■営業活動業務
・請求書の作成と発行業務
営業業務の中で定型化できる業務として、請求書の作成と送付業務があります。RPAがCRMシステムと会計システムの両方にアクセスすることで、会計記録を更新し、請求書を作成、適切な宛先にメールで送信する業務までRPAで実現可能です。
■情シスに関する業務
ヘルプデスク業務
たとえば、ユーザーからのパスワード初期化の依頼も、人が行う場合はユーザーからの依頼を受けた情シス担当者が、該当アカウントのパスワードをリセットし、該当ユーザーに連絡するという手間がありました。これをRPAで行えば、ユーザーがチャットボットにパスワードリセットの連絡をするだけで、自動でパスワードリセットを行い、結果をチャットで連絡するだけで済みます。
システム管理タスク業務
情シスがシステムを日々運用するために、定期的に実施するタスクが存在していると思います。定期バックアップや定期メンテナンス、定期テストなどシステムによって、定期的に実施しなければいけないタスクが存在すると思います。
これらの定期タスクが多いと、情シスが本来やるべき業務ができなくなってしまいますし、RPAが得意な分野でもあります。
■人事に関する業務
社員採用プロセス業務
社員を採用するプロセスには大きな稼働がかかります。
採用時には面接時の評価や採用試験の結果を記録、整理、分析する必要があります。採用後には、アカウントの作成や貸与品の管理などのサポート業務、社員の退職時にはアカウント削除や貸与品の回収などのプロセスがあります。
これらの業務プロセスの一部にRPAを導入することで、プロセス全体のスピードと正確性が向上します。
従業員の管理
従業員からの人事データの変更申請もRPAの導入が可能な分野です。従業員からの変更申請をフォームやメールで受け付けて、その内容でRPAを使って自動で解析し、更新させることで人を介入させずに最新のデータに保つことが可能です。
代表的なRPAツール
RPAツールは海外の製品も含めると、非常に多くの製品がリリースされています。ここでは国内で良く利用されている代表的なRPAツールを5つご紹介します。
WinActor(ウィンアクター)
NTTの研究所が開発したRPAで、導入実績は800社を超えています。日本企業が開発しているため、日本語マニュアルが整備されていたり、インターフェースが分かりやすいという特徴があります。
≫ WinActor(ウィンアクター)
BizRobo!(ビズロボ)
RPAテクノロジーズが販売しているBizRobo!も国産のRPAツールです。導入実績は400社以上で、国産の強みを活かしたサポート力や日本語によるトレーニングコンテンツも充実しています。
≫ BizRobo!
Blue Prism(ブループリズム)
グローバルでRPAの老舗と言われていて、大規模システムをターゲットに、PCI-DSS規格や、SOX法などの厳しいセキュリティ基準をクリアしている点が大きな特徴です。
≫ Blue Prism
UiPath (ユーアイパス)
UiPathも海外では人気のRPAツールで、2017年には日本法人を設立し、国内でも急速に導入実績が増えています。
≫ UiPath(ユーアイパス)
Automation Anywhere Enterprise
米国ではシェアトップといわれているRPAツールです。2017年には日本企業が販売代理店契約を結んだことで、国内でも導入実績が増えています。
≫ Automation Anywhere Enterprise
RPAが注目されている理由
RPAの技術は新しいものではありません。RPA自体は10年ほど前から使われている技術です。ではなぜ最近になって注目されてきたのでしょうか。
RPAが注目されるようになった理由には次のようなものがあります。
技術の進歩
RPAが注目を集める理由になった1つに技術の進歩があります。RPAの操作性の向上や画面の視認性の向上、またRPAに業務パターンを定義する作業もコードを書かずに画面を操作するだけで実装できるようになった製品が出てきたりと、技術の進歩でRPAの普及を後押ししています。
働き方改革
政府主導で働き方改革が進められています。働き方改革とは、長時間労働や労働人口不足といった課題を解決するためにワークライフバランスを推進し、労働者を増やすとともに労働生産性の向上を目指す施策です。
この労働生産性の不足や長時間労働を、RPAの活用で解決することが期待されています。
AIの普及
RPAは定型化された作業を自動化することができますが、RPAにAIを組み合わせることで、定型化されていない部分も含めて自動化できると期待されています。RPAとAIの連動については後ほど詳しく解説します。
RPAの普及による情シス業務の変化
情シスの業務の中には、定型化されていて、かつ細かい作業が必要な業務が多くあるため、RPA導入の恩恵を受けやすい部門です。
情シスがRPAを活用する例としては次のようなものがあります。
* 社員IDの自動登録・権限設定
* PCの初期設定
* サーバー、ネットワーク機器の定期メンテナンス
* システム運用の月次報告書作成
* 障害時のログ収集と一次切り分け業務
* 障害時のシステム切替業務
社員の増減が発生した場合、社員の個人情報を登録したり、PCを手配して初期設定を行う作業が発生します。基本的にこのような作業は定型化されていますので、RPAの導入に適しています。
また、システムの運用監視にもRPAの適用が可能です。システムのバッチ処理や定期再起動など、定期的なメンテナンス業務に適用できることはもちろん、システムの障害時にもログの自動取得や一次切り分け業務、インシデントの自動登録などにも活用可能です。
上記のような定型化された業務はRPAが得意としているところですので、積極的にRPAを導入することで、サービス品質の向上とコストの削減が期待出来ます。
ただし、運用が複雑化・属人化している場合は、RPA導入前に一度最適化を行い、作業の定型化を行う必要があります。
RPAの普及で情シスに新たな業務が生まれるかも
RPAが普及すると、情シスに新しい仕事が追加される可能性もあります。RPAの導入効果を十分に得るためには、RPAに適したプロセスを洗い出し、定型化を行い、時にはシステム化を行う必要があります。
事業部でRPAを導入したいとなったとき、事業部だけでRPAの導入を行っても十分な効果を得ることはできないかもしれません。高い効果を得るためには、情シスがコンサルティングやサポートを行い、導入のサポートから導入後の効果測定までを担うという新たな業務が生まれるかもしれません。
また、RPAは運用しているシステムに導入することになるため、対象製品が会社のセキュリティ要件を満たしているかどうかを確認したり、RPAの活用を想定したIT運用ルールに変更するといった対応が必要になるケースもあります。このため情シス抜きでRPAの導入を進めることは現実的ではありません。もちろん、全社的にRPAを導入するとなれば、業務の標準化や効率化の整備が必要になるでしょう。
このようなことから、RPAの普及で人間が対応しなくてよい業務が生まれる一方で、新たな業務が生まれる可能性があることも知っておきましょう。
RPAとAIの違い
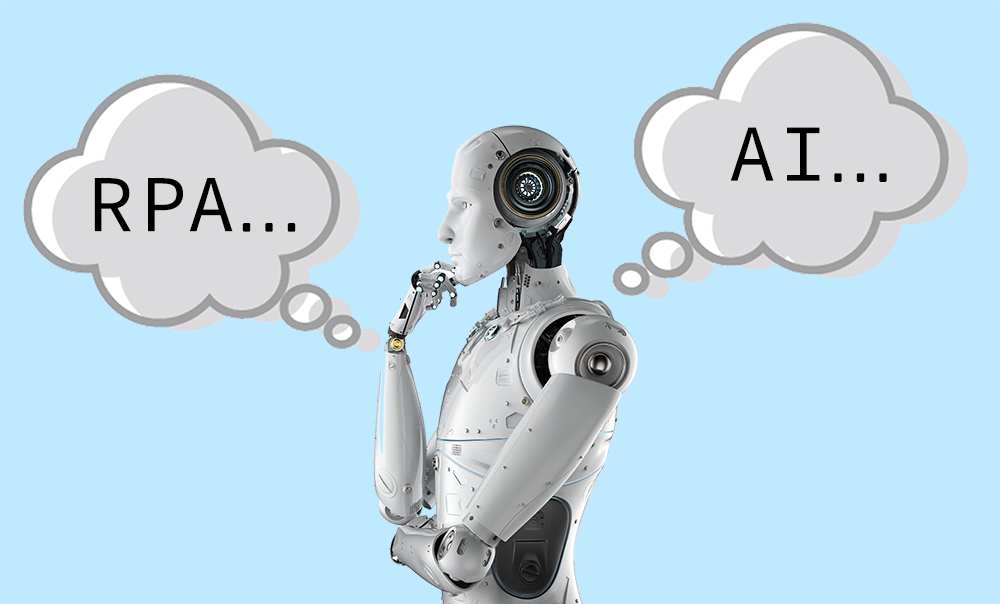
RPAとAIは「自動化」というくくりで同じ技術と混同されがちですが、本質的な部分では大きく異なります。
「RPA」人間が作ったルールに従う
RPAの目的は業務の効率化です。人間が行う作業を一定のルールに基づいて自動化する技術がRPAの技術です。ルールは人間が事前に全て設定するもので、RPAのメンテナンスも人間が行います。そのためRPAは、通常のプログラムに近い技術ともいえます。
「AI」システムが自ら判断する
一方のAIは、多くの情報に基づいてシステムが分類や処理を自らの判断で行います。大量のデータから意味のある答えを導き出し、その結果をさらに次の判断に活用していきます。
≫ 「人工知能搭載でマルウェアを動作前に検知・隔離。AIアンチウィルスとは」
このようにRPAとAIでは、「ルールに従う」か「自ら判断するか」という大きな違いがあります。
RPAとAI の相互補完
RPAを導入するだけでも、十分に業務効率の最適化が期待出来ますが、昨今はAI(人工知能)を組み込んだRPAの実用化も進んでいます。
RPAは定型化された業務に対して、事前に業務パターンを登録しておくことで作業を自動化するため、人の判断が必要な業務や業務パターンが非常に複雑な業務には不向きでした。
しかし、AIを導入することで複雑な業務パターンを自ら学習して、その結果をもとに業務を自動化することも可能になります。
実用化が進んでいる例ですと、ヘルプデスクの問い合わせに対して、問い合わせ内容を解析して回答に近い内容を提示するといったチャットボットサービスで実用化が進んでいます。利用者が、回答の内容が期待したものかどうかを答えるしくみを設けることで、AIが自ら学習して回答精度を高めていくしくみです。
将来的にはシステム障害を検知すると、自動的に障害個所を特定し、障害の拡大を防ぐような一次対処を行い、必要なログを取得し管理者にメールすることまで自動化できる可能性があります。
このように、「RPA+AI」が一般化すれば情シスの業務は劇的に変わることが予想されます。業務負荷も減りますし、慢性的に人手不足だった問題も解消できるでしょう。そうなれば情シスの本来取り組むべき業務である、IT戦略の立案やシステムの高度化検討などに注力することができるでしょう。
まとめ

「AI搭載のRPA」は近い将来、システム運用業務のあり方を劇的に変えるでしょう。その前準備のためにも、ルーチンワーク(アカウントの登録変更やIT資産管理、各種申請業務)の自動化など、RPAを利用した繁雑な業務プロセスの自動化から着手してみてはいかがでしょう。
RPAを効果的に利用するには、次のような課題を解決することも重要なポイントです。
* 定型化されている業務がどれぐらいあるか?
* 人の手で作業が行われている業務がどれぐらいあるか?
* 業務を具体的な作業パターンに落とし込めるか?
RPAにも様々な製品が存在していて、対象業務の向き不向きや操作性、管理の容易性、アフターサポートに有無などをもとに製品を選定する必要があります。
また導入後は、導入効果の評価をしっかりと行うことはもちろんのこと、課題の洗い出しと課題に対する対策を確実に行うことで、業務の効率化を進めることが重要です。


