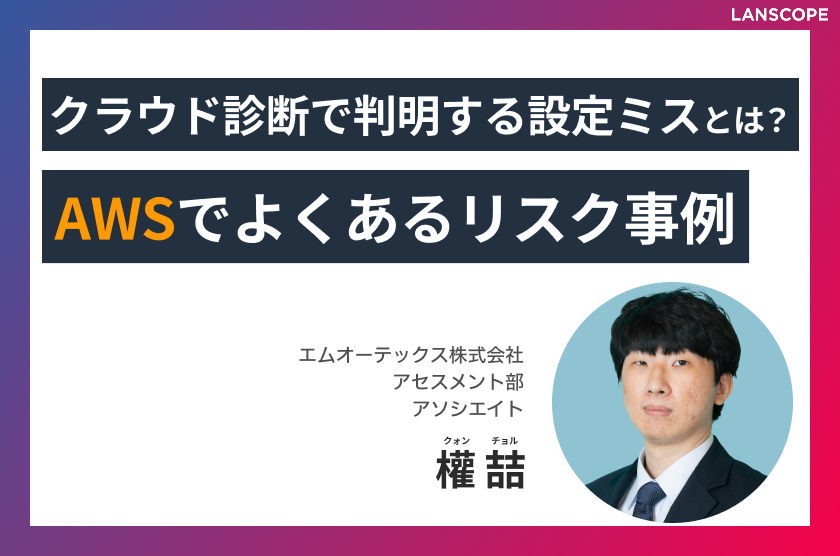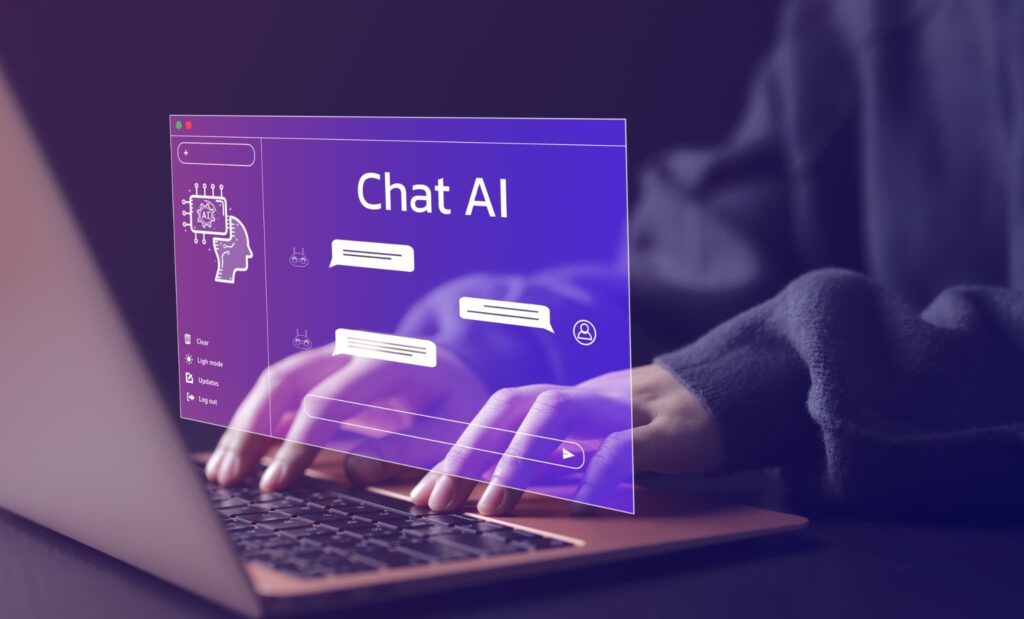Written by C.N.
セキュリティエンジニアとして、ECサイトや各種オンラインサービスの脆弱性診断およびセキュリティ評価、改善提案に従事。
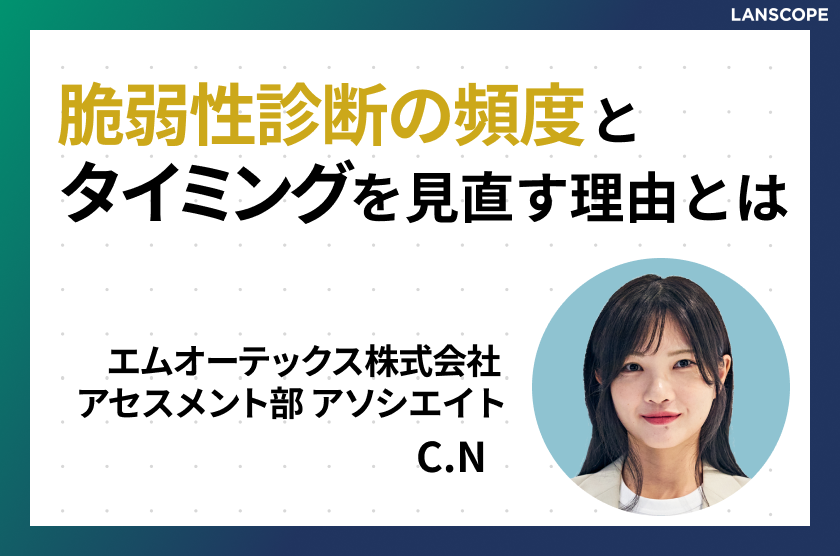
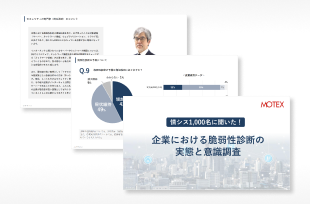
近年、情報システムの高度化とともに攻撃手法も巧妙化し、企業が抱えるセキュリティリスクは日々増大しています。
そこで重要になるのが、定期的な脆弱性診断です。
しかし、「いつ実施すべきか」「どのくらいの頻度でおこなえばよいのか」と悩む企業も多いのが現状です。
本記事では、なぜ定期的な脆弱性診断が必要なのか、その背景とともに、効果的な脆弱性診断の頻度・タイミングの目安、そして組織に合わせた実施計画の立て方についてご紹介します。
なぜ定期的な脆弱性診断が重要なのか

まずは、なぜ定期的な脆弱性診断が求められているのかを解説します。
1. 外部脅威の多様化
サイバー攻撃手法は高度化・多様化しているため 、最新の攻撃技術に対抗するためにも、内容を常に最新の情報に基づいて更新し、定期的にチェックをおこなうことが重要です。
日々新たなゼロデイ脆弱性や攻撃手法が発見される中で、定期的な脆弱性診断は早期発見・早期対応に直結します。
2. システム変更やアップデートの影響
業務システムやネットワークインフラの変更、新たなサービスの導入は、新たな脆弱性を生むリスクがあります。
新しい機能の追加やバージョンアップ、パッチ適用などの変更によって、これまで検出されなかった脆弱性が混入する可能性があります。
定期的な脆弱性診断により、こうした変化に伴うリスクを早期に把握できます。
定期的に脆弱性診断を実施することで、システム変更後の環境に潜むセキュリティホールを迅速に把握し、対策を講じることが可能です。
3. コンプライアンスと信頼性の維持
PCI-DSS、ISO27001、各種個人情報保護規制など、業界・法令ごとに求められるセキュリティ基準に対応するためにも定期診断は不可欠です。
診断実施の履歴を保持することで、監査などに対して適切なセキュリティ対策が講じられていることを証明できます。
定期的に診断を実施し、その対策結果を開示することは、顧客や取引先に対して「セキュリティ対策を強化している」という姿勢を示すことができます。
信頼性向上の観点においても優位性を発揮できるでしょう。
たとえば、 PCI-DSSには以下のように記載されています。
11.3 外部および内部の脆弱性を定期的に特定し、優先順位をつけ、対処している
定義されたアプローチの要件
11.3.1 内部脆弱性スキャンは、以下のように実施する。
・少なくとも3カ月に1回は実施する。
・高リスクおよび重要な脆弱性(要件 6.3.1 で定 義された事業体の脆弱性リスクランキングに基づく)が解決される。
・再スキャンを実施し、上記の高リスクおよび重要な脆弱性がすべて解決されていることを確認する。
・スキャンツールは、常に最新の脆弱性情報に更新されている。
・スキャンは有資格者によって実施され、テスト担当者の組織的な独立性が確保されている。
出典:PCI Security Standards Council「Payment Card Industry データセキュリティ基準 要件とテスト手順 v4.0.1 日本語版」(2024年6月)
また、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が公開している「ECサイト構築・運用セキュリティガイドライン」においても、以下のように記載されています。
ECサイトを構築後、新たな脆弱性が発見される・新たな脆弱性を作り込む可能性があるため、定期的及びカスタマイズを行った際に脆弱性診断を実施することが重要です。
出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「ECサイト構築・運用セキュリティガイドライン」
これらの理由から、脆弱性診断は一度きりではなく、定期的に実施することで、常に最新の脅威に備え、システムの安全性を維持するために欠かせないプロセスであることがわかります。
脆弱性診断の頻度と実施タイミングの目安
次に、脆弱性診断を効果的に活用するためには、「どのくらいの頻度で」「どのタイミングで」実施するのが望ましいのかについて解説します。
1. 基本的な診断頻度
一般的なシステムでは、年1~2回の脆弱性診断が推奨されます。
ただし、業界特性や取扱情報の機密性に応じて、月次や四半期ごとの診断が求められる場合もあります。
2. システム変更時の診断
アプリケーションのバージョンアップ、インフラの構成変更、新サービスの導入直後は、脆弱性診断の実施がとくに重要です。
変更前後のチェックは、リスクの増大を抑えるうえで効果的です。
3. インシデント発生後の診断
万が一攻撃や不審な挙動が観測された場合、原因特定と今後の対応策を講じるためにも、即時の診断が必要です。
これにより、再発防止策を迅速に実施することが可能となります。
組織に合わせた脆弱性診断実施計画の立て方

脆弱性診断をスムーズに効果的に実施するために、どのような実施計画を立てることが推奨されるのかを解説します。
1.資産の洗い出しとリスク評価
まず、現在運用しているクラウド、ネットワーク、アプリケーションなど、すべての重要資産を網羅的に一覧化します。
一覧化が完了したら、洗い出した資産について、業務上の重要度や、万が一脆弱性が悪用された場合の影響度をもとにリスクレベルを評価し、診断の優先順位や頻度の目安を明確に設定します。
この段階での適切なリスク評価が、今後、どの部分を優先してチェックするかを明確にします。
継続的なセキュリティ強化の基礎となるため、丁寧に取り組みましょう。
2. 診断手法とツールの選定
次に、診断の実施方法を決定します。
自動スキャンツールを利用して広範囲を網羅しつつ、特にリスクが高いと判断された領域については、専門家による手動診断を組み合わせることで精度を高めることができます。
内部リソースだけで診断をカバーするのが難しい場合は、外部の専門機関やセキュリティベンダーへの委託も検討し、最新の攻撃手法やゼロデイ脆弱性にも対応できる体制を整えます。
3. 定期診断プロセスの整備
診断は「計画」「実施」「報告」「対策実施」「再評価」という一連のプロセスとして、標準化し、社内全体で共有可能なフレームワークとして確立します。
定期的な診断だけではなく、システムのアップデートや新規導入、さらにはセキュリティインシデント発生後のチェックなど、イベント毎の診断も計画に盛り込むことで、より高い効果が見込めます。
診断結果をもとにした改善計画の策定とフォローアップを組み込むことで、PDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)を回し、継続的なセキュリティ体制の強化が期待できます。
4. 変更管理との連携
たとえば大規模なシステムアップデート、新サービスのローンチ、インフラ変更時など、システムやネットワークに変化があった際の変更管理プロセスに、脆弱性診断の実施を自動的に組み込む仕組みを整えましょう。
具体的には、変更時のチェックリストに「診断実施」の項目を追加し、システム変更が完了した直後に必ず診断を実施するルールを策定するなど、セキュリティ強化策と連動した運用を目指します。
定期的に脆弱性診断を実施するメリット

定期的な脆弱性診断を実施することで、診断基準そのものをアップデートでき、最新のセキュリティリスクに対応できる点が大きなメリットとなります。
たとえば、毎年診断を実施していると、昨年まで「問題なし」と判断されていた設定や構成が、最新の業界基準に基づいて見直され、新たなリスクとして指摘されるケースが出てきます。
脆弱性診断の定期実施で得られるメリットを、より詳しく解説します。
毎年の診断で指摘基準が見直される
脆弱性診断は、最新の攻撃手法や脅威情報が反映された最新の診断基準や評価方法に基づいて実施されます。
そのため、新たに導入された評価基準により、昨年は見逃されていた潜在的なリスクが明らかになるケースも少なくありません。
定期的に診断を実施することで、最新のセキュリティ情勢に即した対策を講じることができ、リスクを迅速に低減するための判断材料となります。
昨年との比較で改善状況が明確に
定期診断のもうひとつの大きなメリットは、診断結果を年度ごとに比較できる点です。
昨年と今年の診断レポートを照らし合わせることで、どのリスク箇所が改善され、どの部分に新たな脆弱性が発生したのかが一目で分かります。
これにより、経営層や関係部門に対して、セキュリティ対策の効果を具体的に示すことができ、今後の優先的な対策計画の策定や改善項目の明確化に大いに役立つでしょう。
まとめ
定期的な脆弱性診断は、日々変化するサイバー脅威に対して自社のセキュリティ体制を常に最新かつ最適な状態に保つために欠かせない取り組みです。
診断の頻度は、組織の業務内容やリスクレベルに応じて柔軟に設定し、システム変更時やインシデント発生後などの臨機応変な対応も含めた総合的な診断計画を策定することが求められます。
組織全体でセキュリティ意識を高め、明確なプロセスと連携体制を整えることで、単なる定期診断に留まらず、継続的なセキュリティ向上のための重要なツールにできるでしょう。
組織規模や予算状況に応じた柔軟な診断体制の構築が、長期的なセキュリティ強化に繋がります。皆様もご自社の状況に合わせ、無理なくセキュリティ対策の第一歩を踏み出してください。
LANSCOPE プロフェッショナルサービスでは、12,000件以上のサービス提供実績と90%以上のリピート率を誇る「脆弱性診断」を提供しています。
国家資格「情報処理安全確保支援士」を保有する診断員が、安心の技術力と専門性で支援します。
ぜひ実施をご検討ください。
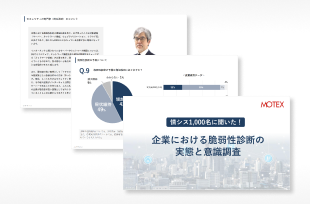
おすすめ記事