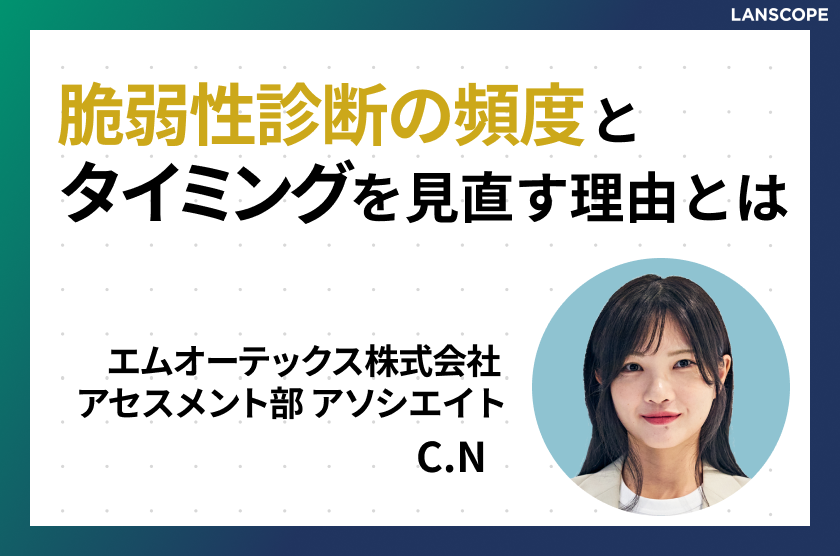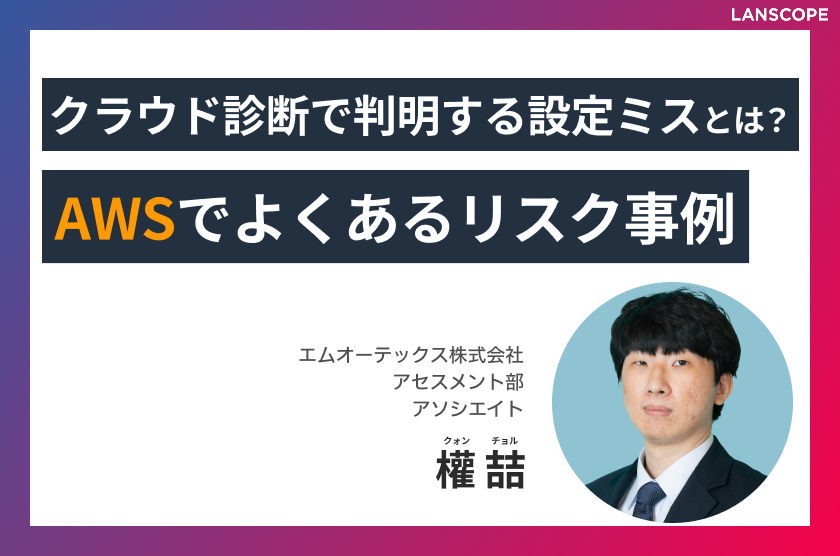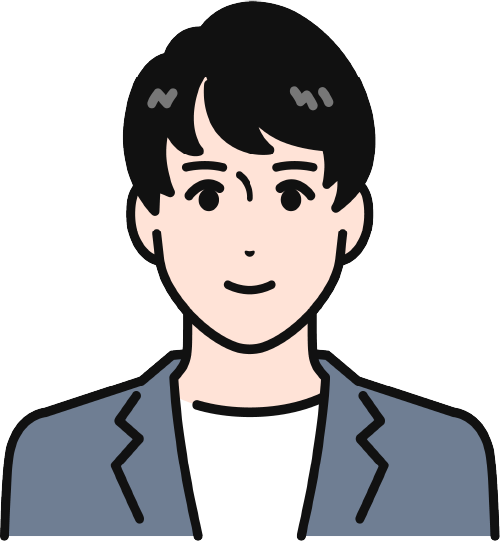
Written by R.N.
セキュリティエンジニアとして、Webアプリケーションやスマートフォンアプリケーションの脆弱性診断に従事。
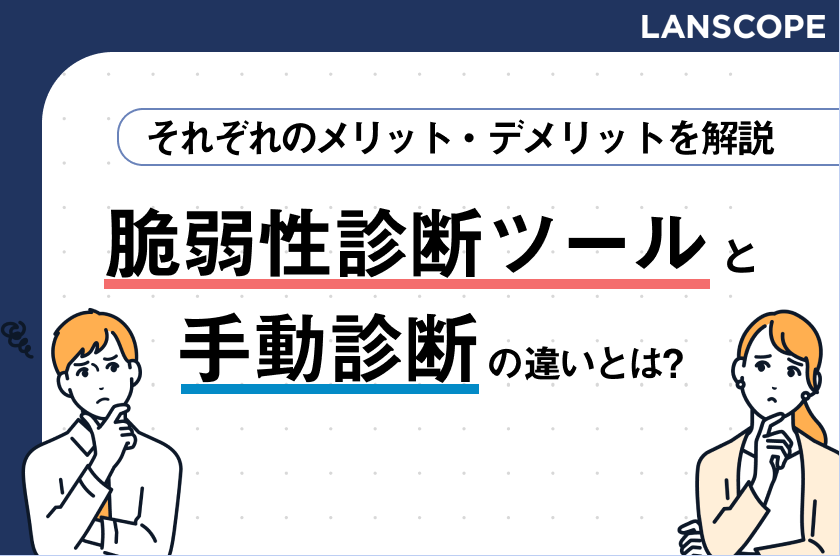
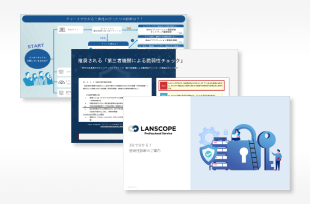
3分で分かる!脆弱性診断のご案内
LANSCOPE プロフェッショナルサービスの脆弱性診断でできることをわかりやすく解説!ぴったりの診断を選べるフローチャートもご用意しています。
はじめに
サイバー攻撃に高度化がみられる昨今、企業の情報資産はさまざまなリスクに晒されています。
こうした脅威に対抗するため、脆弱性診断は重要な防御策となっています。
診断手法は大きく分けて「自動診断ツールによる広範囲なチェック」と「セキュリティエンジニアによる緻密な手動診断」の2種類があります。
どちらの手法にもそれぞれメリット・デメリットがあり、状況に応じた使い分けが求められます。
本記事では、自動診断ツールと手動による診断、それぞれの診断の特徴と選び方、使い分けのポイントについて解説します。
自動診断ツールの特徴と限界

自動診断ツールは、システム全体を短時間で網羅的にチェックできる一方で、対応できる範囲には限界があります。
自動診断ツールの特徴と限界を解説します。
自動診断ツールの特徴
自動診断ツールは、短時間で広範囲をチェックできる診断手法です。
あらかじめ定義されたルールに基づいて、一般的なセキュリティ上のリスクを一律で判定することが可能で、たとえば、クロスサイト・スクリプティングのように、検出ロジックを細かく定義できる脆弱性も検知することが可能です。
ただし、画面遷移などの挙動を厳密に再現しないとエラーとなるサイトも少なくないため、注意が必要です。
脆弱性を検知できないままツール診断が完了することがないように、サイト仕様の理解とツールの知識を備えておく必要があります。
自動診断ツールの限界
次に自動診断ツールの限界について解説します。
まず、ツールの判定はあくまで定型的なルールに基づいておこなわれるため、システム特有の設計や業務ロジックに起因する問題点は見逃される可能性があります。
さらに、実際には安全なロジックをリスクとして判断してしまうなど、ツール特有の誤検知・過検知が生じることも少なくありません。そのため、最終的には人の目による精査が必要となるケースもあるでしょう。
また、システム間の連携や内部処理が複雑な場合、ツールによっては表面的なチェックに留まり、追加で詳細な検査が求められるケースもあります。
加えて、ビジネスロジックに基づくアクセス制御の不備といった検査は、現状の自動診断ツールでは実施が難しいのが実情です。
ツールで検出できない、あるいは誤検知が多い脆弱性の一例として、以下が挙げられます。
- アクセス制御の不備
- クロスサイト・リクエストフォージェリ
- セッション・フィクセーション
- メールヘッダ・インジェクション
- クロスサイト・スクリプティング(格納型)
- セカンドオーダーSQLインジェクション
手動診断の特徴とメリット

次に、手動診断の特徴と実施のメリットについて解説します。
高い専門性を持つセキュリティエンジニアが、システムの背景や業務プロセスを理解したうえで、柔軟かつ深い検証をおこなえることが、手動診断の大きなメリットです。
詳しく解説します。
手動診断の特徴
手動診断は、セキュリティエンジニアがシステムの設計意図や運用状況を踏まえたうえで、潜在的なリスクを丁寧に洗い出す診断手法です。
そのため、企業固有のシステム環境や業務プロセスにあわせた診断が実施でき、細かな問題点も見逃さずに洗い出すことができます。
さらに、日々変化する脅威に対しても、最新の知識と実践から得たノウハウを活かし、適切な対策を講じることが可能です。
ただし、手動で診断を実施するため、自動診断ツールと比較すると時間と費用がかかる点に留意が必要です。
手動診断のメリット
手動診断では、自動診断では見落とされがちなシステム全体の挙動や連携に起因するリスクについても、具体的な攻撃シナリオを想定しながら評価することが可能です。
また、細部までの検証が可能なため、たとえば、個々のシステム構成やアクセス制御の運用状況を精査し、改善すべきポイントを明確に示せます。
さらに、診断結果に基づいた改善提案やパッチ適用後の再検証を通じて、継続的なセキュリティ強化をサポートします。
実例から見る診断手法別の特徴
2024年度にエムオーテックス株式会社が実施したWeb脆弱性診断において、検出数が多かった脆弱性TOP5は以下のとおりです。
| 脆弱性 | 件数 |
|---|---|
| アクセス制御の不備 | 198件 |
| クロスサイト・スクリプティング | 164件 |
| クロスサイト・リクエスト・フォージェリ | 70件 |
| SQLインジェクション | 38件 |
| 意図しないリダイレクト | 29件 |
最も多く検出されている「アクセス制御の不備」は、ツールでの検出が難しく、セキュリティエンジニアがサイトの仕様を理解したうえで、手動で検査する必要がある脆弱性です。
一方で「クロスサイト・スクリプティング」や「SQLインジェクション」といった脆弱性は、ツールで網羅的に検査を実施することが有効な脆弱性です。
このことからも、自動診断ツールと手動診断を組み合わせて実施することの重要性がわかります。
診断手法の選び方と使い分けのポイント
前述のとおり、Webアプリケーションのセキュリティ対策を効果的におこなうためには、自動診断と手動診断を組み合わせることが重要です。
2つの診断手法をどのように使い分ければよいのかを解説します。
選び方のポイント
大規模かつ複雑なシステムの場合、まず自動診断による全体的なスクリーニングを実施し、リスクの高い領域については手動診断で詳細に評価することが効果的です。
また、金融業界や医療業界など、高いセキュリティが求められる業界では、定期的な自動診断の実施に加えて、専門家による手動診断を併用することが推奨されています。
実施効果はもちろん重要ですが、脆弱性診断は一度きりで終わるものではないため、予算や人員といったリソースを考慮し、診断手法のバランスを検討することも重要です。
使い分けの実例
2つの診断手法は、実施するシーンや難易度に応じて使い分けることが推奨されます。実例を挙げて使い分けを解説します。
まず、定期的な診断は、自動診断ツールを活用することで効率的に進められます。
定期スキャンによって、システム全体のリスク評価を継続的に実施するようにしましょう。
一方で、認証・認可処理や購入処理のような重要機能については、セキュリティエンジニアによる詳細な手動診断が有効です。
さらに新システムやツールの導入する際には、自動診断による基本的なチェックと、手動診断による細部までの検証を組み合わせることが推奨されます。
まとめ
自動診断ツールは、広範囲にわたるシステムの安全性評価を迅速に実施するための有効な手法です。
ただし、システム設計が特殊な場合や複雑なビジネスロジックが組み込まれている場合には、自動診断だけでは対応が難しく、専門家による手動診断が欠かせません。
両者を効果的に組み合わせることで、精度の高い脆弱性診断が可能となります。

「LANSCOPE プロフェッショナルサービス」では、プロフェッショナルの知見で最新のセキュリティ脅威に対抗する脆弱性診断を提供しています。
インシデント情報や脆弱性情報などを定期的に収集・解析し、適宜診断ルールに反映しているため、常に最新のセキュリティ基準をもとにした診断の提供が可能です。
診断を担当するのは、国家資格「情報処理安全確保支援士」を有するエキスパートで、確かな技術力と豊富な知見で、安心できるセキュリティ対策をサポートします。
「自社環境やサービスの脆弱性に懸念がある」「診断ツールではなく、プロの目による診断を受けたい」という企業・組織の方は、ぜひ「LANSCOPE プロフェッショナルサービス」の活用をご検討ください。
お客様のご都合・予算などに応じて、最適なプランをご紹介します。
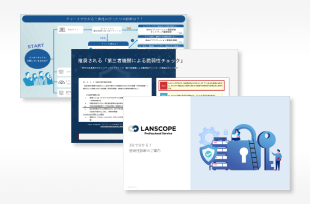
3分で分かる!脆弱性診断のご案内
LANSCOPE プロフェッショナルサービスの脆弱性診断でできることをわかりやすく解説!ぴったりの診断を選べるフローチャートもご用意しています。
おすすめ記事