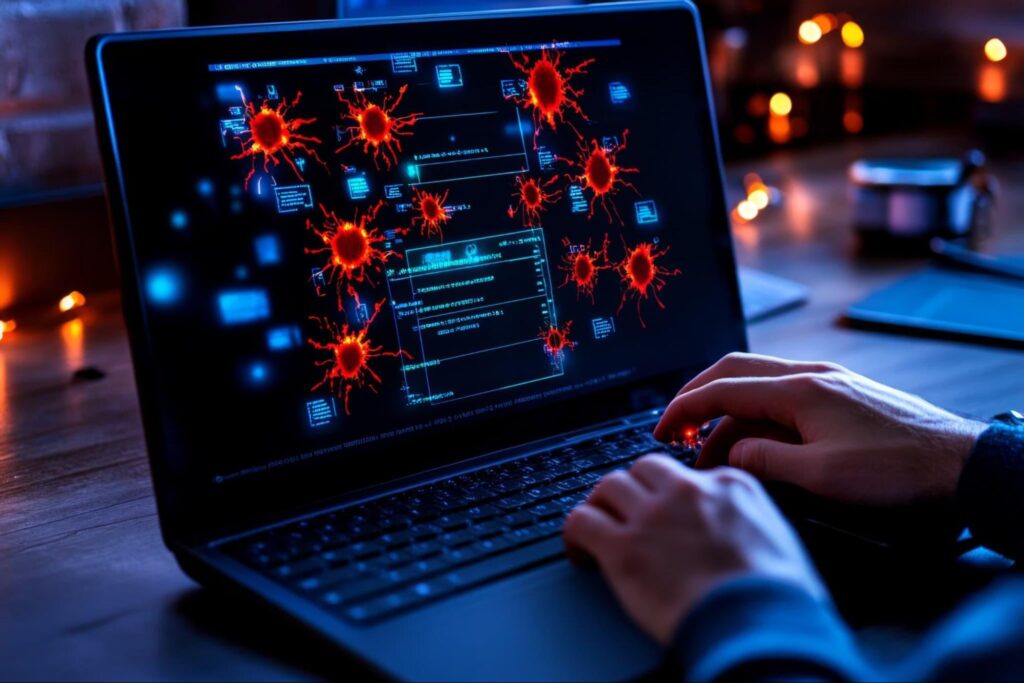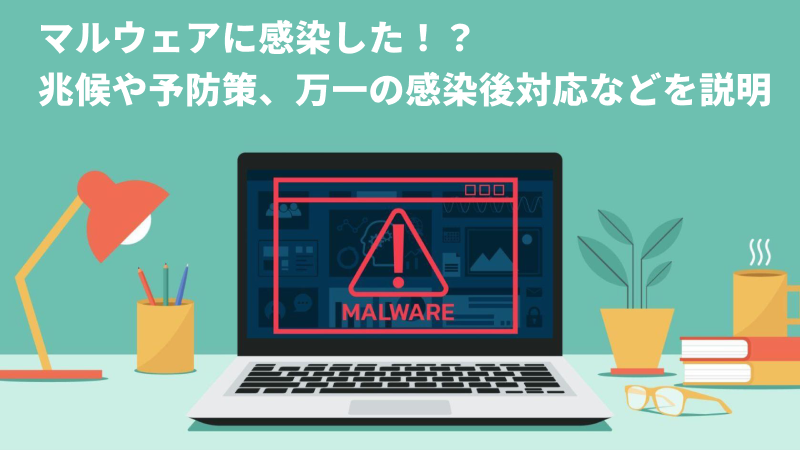Written by WizLANSCOPE編集部

目 次
Googleのウイルス警告とは、ユーザーがウェブブラウジング中に表示される偽の警告メッセージです。
「ウイルスが検出されました」などのメッセージを表示することで、ユーザーの不安を煽り、偽のセキュリティソフトのインストールや偽のサポートセンターへの連絡などを促します。
経営者や従業員が偽の警告に騙されてしまうと、情報漏洩につながったり、多額の金銭を引き出されたりする事例もあるため、企業は対策を講じる必要があります。
本記事では、「Google ウイルス警告」の例や正規の警告との見分け方、表示されたときの対処法などを解説します。
▼本記事わかること
- Googleの偽警告の例
- Googleの偽警告が表示されてしまう原因
- Googleの正規の警告と偽警告の見分け方
- Googleの偽警告への対処法
また本記事では、Googleのウイルス警告をはじめとするさまざまな脅威への対策に有効な「LANSCOPE サイバープロテクション」についても紹介しています。
「Google のウイルス警告が表示された場合にどう対処すればよいのか知りたい」「セキュリティを強化したい」という方はぜひご一読ください。
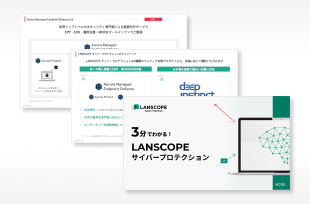
3分で分かる!
LANSCOPE サイバープロテクション
2種類の次世代AIアンチウイルスを提供する「LANSCOPE サイバープロテクション」について、ラインナップと特長を紹介します。
Googleのウイルス警告とは

「Googleのウイルス警告」とは、Webサイトの閲覧中に突然「ウイルスがx個検出されました」「お使いのデバイスがウイルスによりダメージをうけています」といった内容の警告が表示される現象です。
このようなメッセージのほとんどは、Googleが表示させているものではなく、ユーザーの不安を煽るために作られた偽の警告です。
ウイルス駆除を装って、「不審なアプリのインストール」や「外部(偽のサポートセンター)への連絡」「個人情報の入力」などを促してくる場合があります。
Googleのセキュリティ機能による正規の警告は、「情報の入力」や「アプリのインストール」など、特別な操作を強要することはありません。
偽警告と正規の警告の違いを事前に知っておくと、いざというときに冷静に対処できる可能性が高まります。
詳しく確認していきましょう。
偽物のGoogle警告の例

Googleの偽警告では、以下のような文言が使用されるケースが多いです。
- ウイルスがx個検出されました
- お使いのiPhoneがx個のウイルスによって深刻なダメージを受けています
- お使いのシステムは頻繁にxつのウイルスによって破損しています
こうしたメッセージでユーザーの不安を煽り、警告画面に表示されている「今すぐ削除」「除去アプリをインストール」といったボタンをクリックさせて、不審なアプリをインストールさせようとします。

出典:IPA|ウイルス感染したという警告でアプリのインストールを誘導する手口が急増(2016年7月11日)
また、警告画面に電話番号が記載されており、偽のサポートセンターへの連絡を促すケースもあります。
偽物のGoogle警告の目的

攻撃者が、偽警告を表示させる主な目的は以下の通りです。
- 詐欺サイトへの誘導
- 広告宣伝
- 金銭の搾取
- 遠隔操作・アカウント乗っ取り
- マルウェアへの感染
偽広告の種類とそれぞれの想定される被害を解説します。
詐欺サイトへの誘導
攻撃者は、偽の警告画面でユーザーの不安を煽り、ウイルス駆除を口実に詐欺サイトへ誘導します。
誘導先では、個人情報やクレジットカード情報の入力を求め、窃取します。
広告宣伝
詐欺サイトへの誘導と同じ手口で、アプリストアへ誘導するケースもあります。
誘導先では、アプリやサービスの宣伝を行い、インストールやサービスへの加入を促します。
金銭の搾取
偽警告に偽のサポートセンターの電話番号を記載し、電話を促すケースもあります。
焦って電話をかけてきたユーザーに有償サポートの契約などを持ち掛け、金銭を搾取します。
遠隔操作・アカウント乗っ取り
偽のサポートセンターに電話してしまうと「遠隔でパソコンを確認する」などといって、遠隔操作を可能にするソフトウェアのインストールを指示されるケースもあります。
遠隔操作が可能になると、PC内の個人情報や機密データを窃取されたり、インターネットバンキングのアカウントが乗っ取られ、不正送金を行われたりなどの被害が想定されます。
マルウェアへの感染
セキュリティソフトと偽って「マルウェア(悪意のあるソフトウェアの総称)」を仕掛けたソフトをインストールさせるケースもあります。
マルウェアにはさまざまな種類があり、例えばスパイウェアと呼ばれるマルウェアに感染してしまった場合、気が付かない間にアカウント情報やクレジットカード情報などが窃取されたり、外部に送信されたりする恐れがあります。
Google警告が表示される原因

Google警告が表示される原因としては、以下が考えられます。
- 不審なサイトへのアクセス
- マルウェア感染
- ブラウザの脆弱性
あらかじめ原因を理解しておくことで、被害にあうリスクを低減することができます。
ひとつずつ確認していきましょう。
不審なサイトへのアクセス
もっとも一般的な要因としては、不審なWebサイトへのアクセスが挙げられます。
不審なサイトの中には、ページにアクセスするだけで、偽警告画面を生成するスクリプトが自動的に実行されてしまうものもあります。
その結果、偽の警告が表示され、悪質なソフトウェアのダウンロードや、偽サポートセンターへの連絡などが促されます。
マルウェア感染
PCやスマートフォンなどのデバイスがマルウェアに感染している場合、ブラウザ設定が改変され、偽警告が表示されることがあります。
放置してしまうと、不正アプリの追加インストールや情報漏洩など被害の拡大が懸念されます。
ブラウザの脆弱性
ブラウザの拡張機能をインストールする際に、広告を表示させて収益を得ることを目的としたソフトウェア「アドウェア」が一緒にインストールされることがあります。
万一、悪意のあるアドウェアがインストールされてしまうと、ブラウザの脆弱性が悪用され、偽警告を表示する場合があります。
Google警告の本物・偽物の見分け方
本物と偽物の警告を見分けるうえで最も重要なポイントは「操作を強要しているかどうか」です。
偽警告の場合、ほとんどのケースでアプリのインストールや個人情報の入力、サポートへの連絡など、何かしらの行動を取ることが促されます。
一方で正規のGoogleやセキュリティソフトの警告は、危険を検知したことを知らせるだけで、追加の操作を強要することはありません。
また、偽警告では、警告音やカウントダウン表示など、ユーザーの不安を煽る演出が多用される傾向があります。
こうした違いを知っておくことで、警告が突然表示されても、冷静に対処しやすくなります。
ただし、最近ではデザインが非常に精巧で、一見すると本物と区別がつきにくい偽警告も登場しています。
偽警告の被害を防ぐためには、本物・偽物の見分け方を知っておくだけでなく、セキュリティソフトを導入し、二重の防御を行うことが推奨されます。
偽物のGoogle警告への対処法

万が一Googleの偽警告が表示された場合は、以下の対処の実施しましょう。
- 画面を閉じる
- ブラウザ設定を見直す
- OSやソフトウェアを最新の状態にする
- アンチウイルスソフトでスキャンする
詳しく解説します。
画面を閉じる
偽警告が表示されたら、安易にボタンやリンクをクリックせず、速やかに画面を閉じましょう。
Windows、iPhone、Androidでの画面の閉じ方は以下の通りです。
| 画面種類 | 方法 |
|---|---|
| Windows | タスクマネージャーから「タスクの終了」を選択し、Alt+F4同時押しでブラウザを閉じる |
| iPhone | アプリスイッチャーからブラウザアプリの画面を上にスワイプして終了させる |
| Android | アプリの履歴からブラウザアプリを上にスワイプして終了する |
一度画面を閉じれば多くの場合は被害を回避できますが、同じ警告が繰り返し出る場合は、以降で紹介するほかの対処もあわせて実施してください。
ブラウザ設定を見直す
ポップアップブロックやセーフブラウジング機能を有効にしておくと、不審なサイトや悪質な広告へのアクセスを未然に防げます。
さらに、以下のような設定もセキュリティ対策として有効です。
- 自動ダウンロードを無効にする
- トラッキング防止を強化する
- 位置情報の共有を制限する
万一不審な拡張機能が導入されていたり設定が勝手に変更されていたりする場合は、ブラウザをリセットすると改善されることがあります。
問題が解消しない場合は、セキュリティソフトでのスキャンを実施しましょう。
OSやソフトウェアを最新の状態にする
利用しているOSやソフトウェアは、常に最新の状態を保つことが推奨されます。
OSやソフトウェアの中には、公開・出荷後に脆弱性が発見されるものが少なくありません。
この脆弱性を放置してしまうと、攻撃者に悪用され、マルウェア感染や不正アクセスにつながる恐れがあるため、速やかに修正することが重要です。
開発・提供元からリリースされるアップデートには、こうした脆弱性を修正するパッチが含まれており、偽警告を表示させるような不正プログラムの侵入を防ぐ効果が期待できます。
アンチウイルスソフトでスキャンする
偽警告の表示を防ぐためには、信頼性の高いアンチウイルスソフトを導入することも有効です。
アンチウイルスとは、マルウェア(悪意あるソフトウェア)から、システムを保護するために設計されたプログラムのことで、マルウェアがもたらす不正アクセスやデータの破壊・改ざん、情報漏洩などの被害を未然に防ぐ、いわゆる「盾」のような役割を果たすセキュリティソリューションです。
定期的にアンチウイルスでシステム全体をスキャンすることで、ウイルスやアドウェアを検出し、削除し、デバイスを安全な状態に保つことができます。
警告画面をクリックしてしまった場合の対処法

Googleの偽警告をクリックしてしまった場合は、まずは被害の拡大を防ぐために、インターネット接続を切断しましょう。
もし警告の操作によって不審なソフトウェアをインストールしてしまった場合は、直ちにアンインストールし、信頼できるアンチウイルスソフトを使用して、フルスキャンを実施します。
万が一マルウェアが検知された場合は、速やかに隔離や駆除を行うことが重要です。
自社や個人での対応が難しい場合は、フォレンジック調査を専門とする会社への相談も有効です。
専門家による調査では、マルウェア感染の有無や不正通信の痕跡を解析し、セキュリティ強化策や法的証拠となる報告書を提供してもらえます。
根本的な対策としては、不審なリンクやメールを不用意にクリックしない習慣を持つことが最も重要です。
警告画面が表示されても慌てず、冷静に対応する姿勢を保つことが被害防止につながります。
高度なマルウェアへの対策に「LANSCOPE サイバープロテクション」

ここまで確認してきた通り、Googleの偽警告は、アドウェアをはじめとするマルウェアへの感染を目的として行われるケースがあります。
このようなマルウェア感染を防ぐ方法として、「アンチウイルス」の活用が有効です。
アンチウイルスを活用して定期的にシステム全体をスキャンすることで、ウイルスやアドウェアを検出・削除し、デバイスを安全な状態に保つことができます。
本記事では、新種・亜種のマルウェアに対しても高い精度で検知・ブロックする「LANSCOPEサイバープロテクション」の2種類のAIアンチウイルスを紹介します。
▼2種類のアンチウイルスソリューション
- アンチウイルス✕EDR✕監視サービス(MDR)をセットで利用できる「Aurora Managed Endpoint Defense(旧:CylanceMDR)」
- 各種ファイル・デバイスに対策できる次世代型アンチウイルス「Deep Instinct」
2種類のアンチウイルスの特徴を確認していきましょう。
アンチウイルス✕EDR✕監視サービスをセットで利用可能な「Aurora Managed Endpoint Defense」
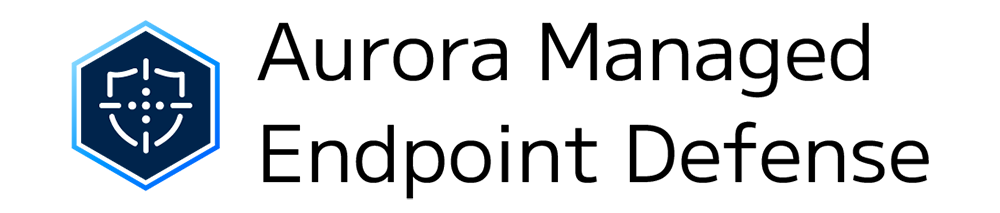
「LANSCOPE サイバープロテクション」では、EDRのマネージドサービス「Aurora Managed Endpoint Defense」を提供しています。
「Aurora Managed Endpoint Defense 」は、アンチウイルスとEDRを併用し、エンドポイントを内外から保護するセキュリティソリューションです。
高度なエンドポイントセキュリティ製品を導入しても、適切に運用できなければ意味がありません。
「Aurora Managed Endpoint Defense」は、下記の2種類のセキュリティソリューションの運用を、お客様の代わりにセキュリティのスペシャリストが実施するMDRサービスです。
- 脅威の侵入をブロックするAIアンチウイルス「Aurora Protect」
- 侵入後の脅威を検知し対処するEDR「Aurora Focus」
セキュリティのスペシャリストが徹底したアラート管理を行うため、お客様にとって本当に必要なアラートのみを厳選して通知することが可能になり、不要なアラートに対応する必要がなくなります。
また、緊急時にはお客様の代わりにサイバー攻撃へ即時で対応するため、業務負荷を減らし、安心して本来の仕事へ集中していただけます。
「Aurora Managed Endpoint Defense」についてより詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。
各種ファイル・デバイスに対策できるNGAV「Deep Instinct」

「LANSCOPE サイバープロテクション」では、 AI(ディープラーニング)を活用した次世代ウイルス対策ソフト「Deep Instinct」を提供しています。
下記のようなセキュリティ課題をお持ちの企業・組織の方は、 検知率99%以上のアンチウイルス製品「Deep Instinct」の利用がおすすめです。※
- 未知のマルウェアも検知したい
- 実行ファイル以外のファイル形式(Excel、PDF、zipなど)にも対応できる製品が必要
- 手頃な価格で高性能なアンチウイルスを導入したい
近年の攻撃者は、セキュリティ製品から検知を逃れるため、実行ファイルだけでなくExcelやPDF・zipなど、多様な形式のマルウェアを仕掛けてきます。
「Deep Instinct」は、形式を問わずにさまざまなファイルに対応しているため、多様な形式のマルウェアを検知可能です。
「Deep Instinct」は、手頃な価格設定も魅力です。詳細は以下よりご覧ください。
※Unit221B社調べ
マルウェアに感染した場合は「インシデント対応パッケージ」におまかせ

「マルウェアに感染したかもしれない」「サイトに不正ログインされた痕跡がある」など、「サイバー攻撃を受けた後」に、いち早く復旧するためのサポートを受けたい場合は、プロがお客様に代わって脅威に対処する「インシデント対応パッケージ」の利用がおすすめです。
「LANSCOPE サイバープロテクション」のインシデント対応パッケージは、フォレンジック調査の専門家がお客様の環境を調査し、感染状況や影響範囲を特定します。
また、マルウェアや脅威の封じ込めから復旧支援、さらに今後の対策に関するアドバイスまでを提供します。
インシデント対応パッケージについて詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。
まとめ
本記事では「Google ウイルス警告」をテーマに、本物と偽物の見分け方や表示された場合の対処法などを解説しました。
▼本記事のまとめ
- Google ウイルス警告とは、Webサイトの閲覧中に突然「お使いのデバイスがウイルスによりダメージをうけています」などと表示される警告画面のこと
- Google警告が表示される原因としては、「不審なサイトへのアクセス」「マルウェア感染」「ブラウザ脆弱性」が挙げられる
- 偽警告は「ソフトウェアのインストール」や「サポートセンターへの連絡」といった何かしらの操作を強要してくる
偽警告が表示された場合は、「画面を閉じる」「ブラウザ設定を見直す」「OSやソフトウェアを最新の状態にする」「アンチウイルスソフトでスキャンする」といった対応を行うことで、被害を最小限に抑えることができる
Googleの偽警告は表示された時点では実際に感染していない場合がほとんどです。
しかし、警告の指示に従ってソフトウェアやアプリをインストールしてしまうと、マルウェアに感染するリスクが一気に高まります。
さらに、警告の指示に従って偽サイトに遷移したり、遠隔操作を許可してしまったりすると、個人情報や金銭を盗まれる危険性もあります。
こうした被害を防ぐためには、不審なリンクやメールを安易にクリックしない習慣を身につけることが重要です。
本記事で紹介した「LANSCOPE サイバープロテクション」のAIアンチウイルスは、新種・亜種のマルウェアも、高い精度で検知し、ブロックすることが可能です。
サイバー攻撃が、ますます高度化・巧妙化している昨今、「Googleのウイルス警告」も形を変えて現れる可能性があります。
被害を防ぐためにも、ぜひ「LANSCOPE サイバープロテクション」のアンチウイルスを導入し、セキュリティ強化を目指してください。
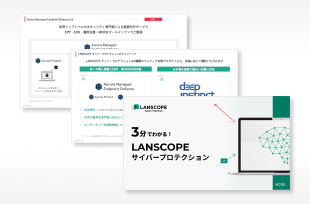
3分で分かる!
LANSCOPE サイバープロテクション
2種類の次世代AIアンチウイルスを提供する「LANSCOPE サイバープロテクション」について、ラインナップと特長を紹介します。
おすすめ記事